24年十大ニュース、「能登地震」が1位=海外は「トランプ氏が返り咲き」
2024年12月23日 14時10分
時事通信社は2024年の国内と海外の十大ニュースを選定した。それぞれ次の通り。(肩書は当時)
【国内】
 時事
時事 ①石川・能登で最大震度7、大被害に
1月1日午後4時10分、石川県能登地方を震源とする地震が発生し、同県輪島市と志賀町で最大震度7の揺れを観測した。地震の規模(マグニチュード)は7.6で、2011年の東日本大震災以来となる大津波警報が発令された。同市名物の「輪島朝市」では多くの建物が焼失するなど、各地で建物倒壊や火災などの被害が相次いだ。
地震による死者は新潟、富山両県を合わせ約500人で、そのうち災害関連死が約半数を占める。石川県では約6000棟が全壊し、約1万8000棟が半壊した。能登半島は9月には記録的な大雨にも見舞われ16人が死亡したほか、元日の地震を受け建てられた仮設住宅が浸水するなどの被害が出た。二つの災害に伴う人口流出は深刻で、地域社会の再建などが大きな課題になっている。
②衆院解散、自公過半数割れで少数与党に
石破茂首相(自民党総裁)は10月9日に衆院を解散し、同27日投開票の政治決戦に挑んだ。内閣発足から8日後の解散、26日後の投開票はいずれも戦後最短。9月の総裁選勝利と新政権誕生の「刷新感」を最大限活用しようとしたが、非公認とした派閥裏金事件関係候補側への2000万円支給問題が直撃。公明党と共に大敗し、過半数を失って30年ぶりの少数与党となった。
一方、立憲民主党は50議席増。国民民主党は4倍の28議席と躍進した。衆院で過半数を持つ政党が不在の「宙づり国会」で、政権側は2024年度補正予算の成立と政治改革の年内実現を懸けて譲歩を連発。国民民主が訴える「年収103万円の壁」見直しでは、178万円を目指して25年から引き上げると約束せざるを得なかった。
③被団協にノーベル平和賞
2024年のノーベル平和賞が、日本原水爆被害者団体協議会(日本被団協)に授与された。「再び被爆者をつくるな」を合言葉に、70年近くにわたって被爆体験を国内外で積極的に発信してきたことが評価された。日本人の平和賞受賞は1974年の故佐藤栄作元首相以来50年ぶりで、団体では初めて。
日本被団協は被爆者でつくる唯一の全国組織で、56年に結成された。核軍縮に関する国連などの国際会議にも被爆者を派遣し、核兵器廃絶を強く訴えてきた。12月10日にノルウェーの首都オスロで開かれた授賞式では、代表委員の田中熙巳さん(92)が講演。核廃絶を「心からの願い」とした上で「人類が核兵器で自滅することのないよう、核兵器も戦争もない世界を求めて共に頑張りましょう」と呼び掛けた。
④日銀、マイナス金利解除
日銀は3月の金融政策決定会合で、マイナス金利政策を解除し、11年続いた異例の大規模金融緩和に終止符を打った。日銀の利上げは17年ぶり。2024年春闘で前年を大幅に上回る賃上げ率を確認し、賃金と物価がともに上昇する「好循環」が強まったことで、2%の物価上昇目標の持続的・安定的な実現が見通せたと判断した。
日銀は13年春に就任した黒田東彦前総裁の下、国債を大量購入する大規模緩和を開始。マイナス金利は金融緩和を強化するため、16年2月に導入された。23年4月に就任した植田和男総裁は金融政策の正常化へ大きく前進。マイナス金利解除後、7月末には追加利上げを決定した。「金利ある世界」への転換は、低インフレと低金利、低成長の「低温経済」から抜け出せるかの岐路となる。
⑤袴田巌さん、再審無罪
静岡県で1966年、みそ製造会社の専務一家4人を殺害したとして、強盗殺人罪などで死刑が確定した袴田巌さんの再審判決が9月26日、静岡地裁であり、無罪が言い渡された。判決は捜査機関による証拠の捏造(ねつぞう)を認定し、袴田さんは「犯人と認められない」と結論付けた。戦後に起きた事件で死刑確定後に再審無罪となったのは5例目。
袴田さんに代わり法廷に立った姉ひで子さんに、国井恒志裁判長は「申し訳ないと思っている」と謝罪した。畝本直美検事総長は判決に不満を示しながらも「袴田さんは相当な長期間にわたり法的地位が不安定な状況に置かれた」として、控訴断念を表明。逮捕から58年を経て、無罪が確定した。静岡県警本部長と静岡地検検事正は袴田さん宅を訪ね、直接謝罪した。
⑥岸田首相退陣、自民総裁選で石破氏選出
お盆期間中の8月14日、岸田文雄首相(自民党総裁)は前触れなく総裁選への不出馬を表明した。自民派閥の政治資金パーティー裏金事件で世論の逆風が吹く中、自身が率いた岸田派を率先して解散し、安倍、二階両派の事件関係議員を大量に処分。しかし、政権を取り巻く情勢は一向に好転せず、追い込まれる形で約3年にわたる政権運営にピリオドを打つことを宣言した。
にわかに火ぶたが切られた「ポスト岸田」レースでも、最大の論点となったのは裏金事件への対応。長く非主流派だった石破茂元幹事長が、早期の衆院解散・総選挙をにらんでイメージの刷新を求める党内の空気に乗り、決選投票の末に5度目の挑戦で勝利を収めた。その4日後の10月1日、国会で第102代首相に指名された。
⑦株価が初の4万円台、バブル期上回る
日経平均株価は2月22日にバブル全盛の1989年末に付けた3万8915円を約34年ぶりに上回り、7月11日には史上最高値となる4万2224円を記録した。円安に伴う輸出企業の業績押し上げが寄与した。日本が長年のデフレから脱却するとの見方や、東証が企業に求める統治改革の進展への期待が市場で強まったことが背景にある。
幅広い銘柄で構成する東証株価指数(TOPIX)も89年末の高値(2884)を超え、7月11日にはピークの2929をマークした。一方、人工知能(AI)の本格普及を前に半導体関連銘柄への期待が短期的に過熱したとの指摘もある。日銀の植田和男総裁が追加利上げに前向きな姿勢を示したのを機に日経平均は8月5日に約12%も下落し、「令和のブラックマンデー」と呼ばれた。
⑧物価高騰が生活直撃、令和の米騒動も
新米が本格的に出回る直前の今年夏、スーパーなど小売店の店頭でコメの極端な品不足が発生した。猛暑が響いて前年産の精米の歩留まりが低下したことや、南海トラフ地震の臨時情報を受けた消費者による買いだめ、インバウンド(訪日客)需要の高まりなどが重なった。原因分析や検証を行った農林水産省は、スーパーや米屋といった小売店に対する流通実態の定期ヒアリング、消費者への情報発信強化などの対応策を打ち出した。
品薄が解消された後も価格高騰は続いた。指標となる業者間の相対取引価格は11月、全銘柄平均で玄米60キロ当たり2万3961円と前年同月から6割近く上がり、3カ月連続で過去最高を更新。コメの需要は中長期では減少傾向にあり、高値が続けばコメ離れに拍車が掛かる可能性もある。
⑨闇バイト強盗事件が多発
首都圏の1都3県で8月以降、戸建て住宅などを狙った強盗事件が約20件相次いだ。住人を粘着テープで縛り、暴行を加えるなどの手荒な手口が目立ち、10月には横浜市で、75歳の男性が鈍器で殴られるなどして死亡した。警察当局は匿名・流動型犯罪グループが関与しているとみて、12月半ばまでに実行役や現金運搬役、リクルーター役など45人以上を逮捕。そのほとんどがSNSで「ホワイト案件」「即日即金」などとうたう闇バイトに応募し、匿名性の高いアプリで指示を受けて犯罪に加担していた。
政府は募集者の氏名や業務内容などを記載していない求人情報は違法と明確化し、事業者に削除を求めることを決定。捜査員が架空の身分証を使って闇バイトに応募する「仮装身分捜査」も早期に実施する。
⑩選挙でSNS旋風、既存政党離れ
SNSでの発信が、選挙で躍進する原動力となるケースが相次いだ。7月の東京都知事選では、政党の支援を受けなかった前広島県安芸高田市長の石丸伸二氏がSNSを駆使し、2位に浮上。11月の兵庫県知事選では、失職した前職の斎藤元彦氏を応援する多数の投稿が後押しとなり、逆転勝利に結び付いた。10月の衆院選で国民民主党が大幅に議席を増やしたのも、ショート動画などの積極的な投稿が奏功したとされる。
ネット選挙が解禁された2013年以降、有権者が情報を得る手段として大きな位置を占め、既存政党離れが進む中で無党派層に直接訴えるSNS戦略が不可欠になった。一方でフェイクニュースや根拠の乏しい情報、誹謗(ひぼう)中傷などの問題も顕在化。対策が急務となっている。
【海外】
①米大統領選、トランプ氏が返り咲き
11月5日投開票の米大統領選で、共和党のドナルド・トランプ前大統領が民主党のカマラ・ハリス副大統領を下し、ジョー・バイデン大統領に敗れた2020年の雪辱を遂げた。共和党は同時に行われた上下両院選でも勝利し、ホワイトハウスと議会両院を掌握する「トリプルレッド」を達成。トランプ氏は盤石の体制で25年1月20日に大統領に返り咲く。
トランプ氏は2度の暗殺未遂を切り抜け、一般得票総数でもハリス氏を上回る「完勝」を収めた。当選後は、不法移民や麻薬の流入が止まるまで中国、メキシコ、カナダに新たな関税を課すと表明。ロシアの侵略を受けるウクライナに早期和平を迫る可能性もある。「米国第一」を掲げるトランプ氏の姿勢に、日本を含む同盟各国の間で懸念が広がっている。
②大谷、メジャー初の「50―50」
米大リーグ、ドジャースの大谷翔平が史上初のシーズン「50本塁打、50盗塁」を達成した。9月19日のマーリンズ戦で3打席連続本塁打に2盗塁と大活躍し、一気に両部門とも大台をクリア。パワーとスピードを高いレベルで兼備した選手の証明となる「40本塁打、40盗塁」を達成した選手は過去に5人いたが、大谷はその上をいく前人未到の領域に。「50―50」は「2024ユーキャン新語・流行語大賞」でトップテン入りした。
昨年に右肘の手術を受け、今季は指名打者に専念し54本塁打、130打点で2冠王。自身初めてプレーオフに出場してチームのワールドシリーズ制覇に貢献し、オフには満票で2年連続3度目の最優秀選手に輝いた。来季は投手として復帰予定で、本来の投打二刀流の復活が期待されている。
③韓国「非常戒厳」、大統領弾劾可決
韓国の尹錫悦大統領は12月3日夜、野党の横暴で「国政がまひ状態にある」などを理由に、1987年の民主化後初となる非常戒厳を宣言。一切の政治活動の禁止や言論統制などの布告文が発表され、国会などに戒厳軍を派遣した。国会に集まった議員は戒厳解除を決議した。約6時間で解除されたが、尹氏らが与野党代表らの逮捕を指示していたという証言も出ている。
検察、警察などは内乱容疑で尹氏らの捜査を加速。尹氏は正当性を主張したが、国会は14日、野党が提出した大統領弾劾訴追案を可決し、大統領の職務は停止された。弾劾案への対応を巡って与党内は混乱し、造反が続出。憲法裁判所が半年以内に罷免の可否を判断する。次期大統領選前倒しを視野に、政局の混迷が続く見通しだ。
④イスラエルがレバノン侵攻
イスラエルは9月30日、レバノンのイスラム教シーア派組織ヒズボラ掃討を掲げ、同国南部で地上作戦を開始した。レバノン侵攻は2006年以来18年ぶり。23年10月にパレスチナ自治区ガザでイスラエルとイスラム組織ハマスの大規模衝突が始まって以来、ハマスに連帯を示すヒズボラとイスラエルの間でも散発的な戦闘が続いていた。
イスラエルは地上侵攻に先立ち、ヒズボラの通信機器を一斉に爆発させる作戦を実行。首都などへの空爆も強化し、ヒズボラ最高指導者ナスララ師を殺害した。11月26日、米仏の仲介で、イスラエルがレバノン南部から、ヒズボラがリタニ川以北へ撤退するなどとした停戦合意が成立。しかし双方が合意違反を主張し、イスラエルは空爆を継続。ヒズボラも反撃し、先行きは不透明だ。
⑤パリ五輪で日本が45個のメダル獲得
100年ぶりにパリで夏季五輪が開催された。男女の出場枠が史上初めて同数となり、「ジェンダー平等」の理念が体現された。セーヌ川が舞台の開会式では選手が船上パレードで登場し、エッフェル塔などでの競技も注目された。日本勢は海外開催でいずれも最多の金20個、総数45個のメダルを獲得。体操男子団体総合や陸上女子やり投げの北口榛花(JAL)らが金メダルに輝いた。
難民選手団が初となるメダルをボクシングでつかんだ一方、混迷する国際情勢は大会に暗い影を落とした。ウクライナ侵攻の影響で、ロシア選手は国を代表しない「個人の中立選手(AIN)」として参加。選手が性別を巡る論争に巻き込まれたり、SNSで誹謗(ひぼう)中傷されたりした問題は、国際社会にさまざまな問いを投げ掛けた。
⑥シリアのアサド独裁政権崩壊
2011年から内戦状態だった中東シリアで、父子2代、50年以上続いたアサド独裁政権が12月8日、旧反体制派の攻勢で崩壊した。政権を支援してきたロシアがウクライナ侵攻に集中し、隣国レバノンのイスラム教シーア派組織ヒズボラがイスラエルの攻撃で弱体化した隙を突き、旧反体制派は攻勢を強めてから10日ほどで首都ダマスカスに到達した。
政権崩壊後、拷問や超法規的処刑といった人権侵害の実態が明らかになりつつある。「シャーム解放機構」(HTS、旧ヌスラ戦線)が主導する旧反体制派は暫定政府を置き、アサド時代の憲法・国会を一時的に停止する一方、法の支配に基づく統治を確立すると強調。しかし、HTSは国際テロ組織アルカイダの流れをくんでおり、先行きを懸念する声もある。
⑦ウクライナ侵攻継続、ロ朝「軍事同盟」復活
2022年2月に始まったロシアのウクライナ侵攻は3年目に入った。ロシアは侵攻継続のため北朝鮮との軍事協力を強化し、プーチン大統領と金正恩朝鮮労働党総書記が6月に平壌で会談。有事の際の相互軍事支援を定めた「包括的戦略パートナーシップ条約」を締結し、冷戦時代の「軍事同盟」が復活した。
10月以降、北朝鮮がロシアへの派兵を決定したとの情報が出始め、米国務省は11月、ウクライナ軍が越境攻撃したロシア西部クルスク州で、北朝鮮軍部隊がロシア軍と作戦を始めたと明らかにした。派遣された北朝鮮兵は1万人以上とみられている。ロシアは犠牲を顧みない攻撃で占領地を拡大し、ウクライナは劣勢を強いられた。支援に消極的なトランプ次期米大統領の再登板もウクライナには懸念材料だ。
⑧米が利下げ、4年半ぶりに緩和転換
米連邦準備制度理事会(FRB)は9月、2020年3月以来4年半ぶりに利下げを決めた。急激なインフレを抑え込むために続けてきた金融引き締めを緩和方向に転換。政策金利を0.5%引き下げ、年4.75~5.00%とした。下げ幅は通常の2倍となる異例の大きさで、景気と雇用の拡大を持続させる政策運営にかじを切った。
米国ではコロナ禍後の消費急増を背景に、インフレ率が歴史的な高水準を記録。FRBは22年3月から急ピッチで利上げを進め、物価高騰は落ち着いた。引き締めの副作用で景気に減速感が出る中、24年は11、12両月にも利下げを実施。ただ、トランプ次期大統領が掲げる高関税などの政策はインフレ再燃につながりかねず、FRBの政策運営環境は不透明感が強まっている。
⑨台湾総統に頼氏、中国反発
台湾で1月13日、与党・民進党の頼清徳氏が総統に選出された。同一政党の政権が3期続くのは、1996年の直接投票による総統選が始まって以来初めて。頼氏は、日米との連携を重視し中国に厳しい態度で臨んできた蔡英文前総統の路線を継承。5月の就任演説では、中国との関係で「現状維持」を訴える一方、台湾を「主権独立国家」と強調した。
頼氏を「台湾独立派」として敵視する中国の習近平政権は激しく反発。「台湾独立勢力への懲罰」などとして、中国軍が台湾を取り囲む形で大規模演習を2度行い、事実上の経済封鎖をちらつかせて威嚇した。習政権は、台湾と正式な外交関係を結ぶ数少ない国の切り崩しや、台湾からの輸入品に対する関税引き上げなど、外交・経済面でも威圧を強めている。
⑩AIブーム続く、法規制も
人工知能(AI)の発展・普及が加速した。開発各社が生成AIの新モデルを相次いで発表し、性能や価格を巡る競争が激しい中、AI向け半導体でシェア首位の米エヌビディアにはブームの追い風が吹いた。時価総額はマイクロソフトやアップルを抜き、初めて終値で世界トップに。8~10月期の売上高と純利益は四半期ベースで過去最高と、好業績を謳歌(おうか)し続けている。
一方、偽情報の拡散や人権侵害、犯罪行為への悪用を防ぐため、規制に向けた動きも目立った。5月には欧州連合(EU)で、AIの開発や利用に関する世界初の規制法が成立。6月の先進7カ国首脳会議(G7サミット)では主要議題に上った。日本でも8月以降、規制の在り方を議論する政府の有識者会議が開催された。(了)

103万円の壁
所得税の納税義務が発生する年収額。基礎控除の48万円と給与所得控除の55万円を合わせた103万円までが非課税枠となる。また、親の扶養に入る学 …


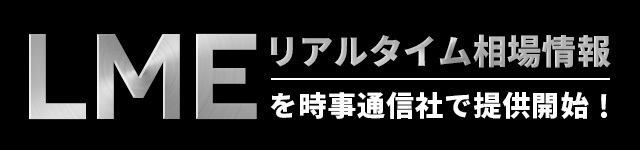
![オペレーションF[フォース]](https://financial.jiji.com/main_news/img/opf_banner.jpg)