教職員向けお金のセミナー開催 ~生活にも授業にも役立つ〔PR〕
2025年04月17日 09時00分
金融経済教育推進機構(J-FLEC)は2025年3月8日、「はじめてのマネーレッスン〜教職員ご自身のための家計管理と資産形成セミナー〜」をオンラインで開催した。実践女子大学の髙橋桂子教授とJ-FLEC認定アドバイザー兼ファイナンシャルプランナーの川口由美氏が講師を務め、学校での金融経済教育の意義から教職員自身の家計管理・資産運用の基礎知識などを2部構成で解説した。
J-FLECは2024年4月設立の認可法人。政府や日本銀行、全国銀行協会、日本証券業協会が出資し、金融経済教育の推進を目的に中立・公正な立場で活動している。主な事業として学校や企業等への講師派遣、学校への教材提供、個人が専門家に相談できる仕組みなどを提供している。
いわゆる新学習指導要領で金融分野の記載が充実したことから、教育現場では金融・経済に関する話題が増え、教職員の金融リテラシー向上が求められている。本セミナーは教職員に向けて家計管理や投資の基礎知識をお伝えし、自らの生活や授業に役立ててもらいたいとの想いで実現した。
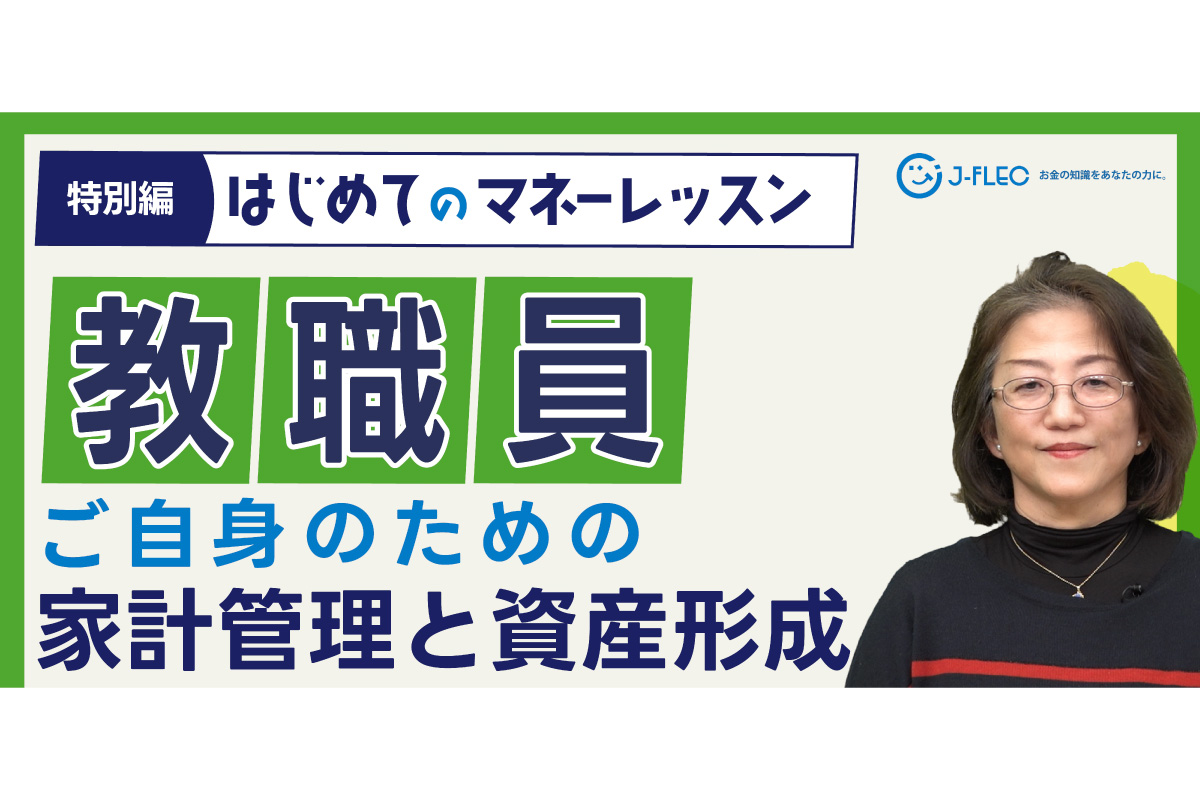
第1部:新学習指導要領と金融経済教育
第1部では、学習指導要領の改訂を振り返り、今なぜ金融経済教育が必要なのか、髙橋教授が社会的背景から解説した。
改訂後の中学校・高等学校の学習指導要領では、金融分野の取り扱いが大きく拡充された。中学校では社会科の公民的分野で、主に企業活動を切り口に金融の仕組みに触れる。高校の公共では投資の社会的意義や資産運用に伴うリスクとリターンなど、家庭基礎ではマネープランや資産形成について学ぶ。「変化の激しい時代においては、社会に出る前に『生きる力』を身につける必要がある。そのために金融経済教育が必要だ」と髙橋教授は語る。
金融経済教育が必要な3つの理由
学校で金融経済教育が必要とされる背景として、髙橋教授は3つの社会的な理由を挙げた。第1に、テクノロジーを活用したスマート社会「Society5.0」の実現に向け、個人にも自律的な判断力が求められている点だ。人生100年時代といわれるなか、キャッシュレス決済やロボアドバイザーなど多様な金融サービスを正しく選んで使いこなすには、金融の知識が欠かせない。
第2に、成年年齢の引き下げにより若者が金融関連の契約行為を行う機会が増えている点が挙げられる。2022年4月に成年年齢が20歳から18歳へ引き下げられ、18歳からクレジットカードの作成、携帯電話や賃貸住宅の契約などが保護者の同意なく可能になった。成年に達した後は未成年者取消権が適用されないため、詐欺などに巻き込まれるリスクも高まっている。こうしたトラブルを防ぐためにも、金融リテラシーを身につけておく必要がある。
第3に、若年層の社会参画意識の低さが挙げられた。他国と比べて日本の若者は社会参画への関心が低い傾向がみられる。自己成長を実感できる経験が少ない点が要因とされ、髙橋教授は「金融経済教育が成長体験の一助となるのではないか」と語った。お金の使い方や買い物など日常生活に密着したテーマを通じて、自分で考え、判断していく体験は自己肯定感の向上にもつながる。こうした観点から、金融経済教育は単なる知識の習得に留まらず、生徒の生き方にも関わる実践的な教育として位置づけられる。
実際の授業における金融経済教育
続けて、髙橋教授は学校での自身の取り組みを紹介した。小学校では「貯める」「使う」「譲る」「増やす」の4つの使い道を設けたお小遣い帳を使った授業を行った。自分の意思でお金を管理する感覚を育てることを狙いとしている。中学・高校では、実践的推論アプローチを用いて様々な実践を行う。自分自身への問いを重ね、合理的な意思決定を下す体験を積むというものである。また、大学では金融リテラシーを学べるオンデマンド形式の講義を開講している。「お金について学びたいと考える学生は多い。身近な話題を授業の冒頭で少し取り上げるだけでも、生徒は惹きつけられるのでは」と髙橋教授は提案した。
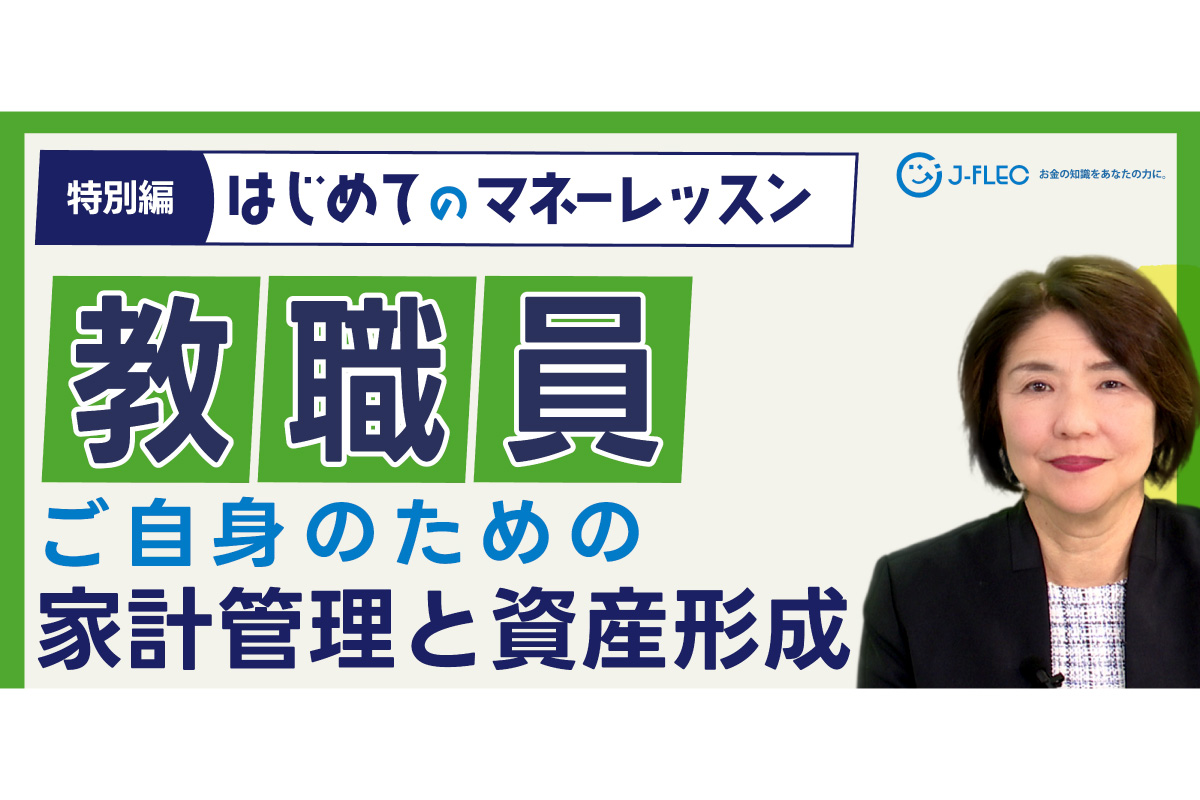
第2部:教職員ご自身のための家計管理と資産形成セミナー
ここまで金融経済教育の必要性について取り上げてきたように、教育現場に立つ教職員にとっても、お金は日常生活から切っても切り離せないものだ。第2部では、川口氏が教職員自身のための家計管理や資産形成について、実践的なポイントを解説した。
投資に関する誤った理解
川口氏は、ライフプランニングや収入と支出のバランスを意識した家計管理の具体的な手順を示し、資産形成の必要性について説明した。資産形成の主軸は預貯金と投資だが、投資をギャンブルと捉えている人も多い。しかし、「投資によって企業や政府に渡った資金は、よりよい商品の提供や公共サービスの充実のために使われる。投資は最終的には投資家に還元される社会貢献でもある」と強調した。
資産形成シミュレーション
リスクを抑えて投資するコツは「長期・積立・分散」の3つだ。資産運用における「リスク」は、元本割れの危険性ではなく、運用成果の振れ幅を指す。運用成果の振れ幅が小さい預貯金はローリスク・ローリターン、株式はハイリスク・ハイリターンの金融商品であり、ローリスク・ハイリターンな商品は存在しない。
リスクとリターンの関係を踏まえて、川口氏は資産形成のシミュレーションを実演した。シミュレーションにはJ-FLECが提供する「資産形成タイムトラベル」を使用した。金融商品の組み合わせや運用期間などの条件を設定すると、過去のデータに基づいたシミュレーションを行えるツールだ。資産運用の長期・積立・分散投資の効果を体験できる点が特徴で、最大10パターンまで同時に比較できるため学校のグループ学習等でも活用しやすい。
本セミナーでは、2004年から2023年までの20年間、毎月1万円の積立を次の3パターンで比較した。Aは国内株式と外国株式を半分ずつ組み合わせたリターン重視型、Bは国内外の株式・債券を25%ずつ組み合わせたバランス型、Cは全額を預貯金のみで運用するパターンである。 シミュレーションの実演後、川口氏は3つのパターンについて、それぞれのメリットとデメリットを振り返った。
金融トラブルの相談窓口
投資詐欺や副業詐欺にも注意が必要だ。もしトラブルに巻き込まれてしまったらひとりで抱え込まず、消費者ホットライン(消費者センター)や警察、金融サービス利用者相談(金融庁)など、信頼できる機関へ相談してほしい。川口氏は「ローリスク・ハイリターンはあり得ません」と言いきり、「怪しいと思ったらはっきり断って」と呼びかけた。
J-FLECを活用し、学校全体で金融リテラシー向上を
本セミナーでは金融経済教育の必要性から家計管理・資産形成まで、授業にも教職員自らの生活にも生かせる内容が取り上げられた。参加者からは「まずは職員室から金融教育を進めたい」「学生にもっと関心を持ってもらいたい」などの声が寄せられている。J-FLECでは職場や学校への講師派遣を無料で提供しているため、ぜひ活用してほしいと締めくくられた。
J-FLECは、本セミナーの内容をアーカイブ配信している。家計管理・資産形成の実践的な知識の習得にお役立ていただきたい。
URL:https://www.youtube.com/playlist?list=PLI_DJNAnLWZXpL5NFiow1nmceS6GcbflV


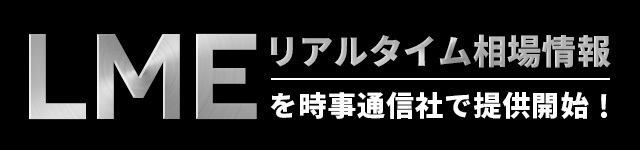
![オペレーションF[フォース]](https://financial.jiji.com/main_news/img/opf_banner.jpg)