アセットマネジメントOne、リタイアメントビジネスを本格展開=米大手と協働、第1弾は「ターゲット・イヤー・ファンド」
2025年03月31日 08時00分
 (左が杉原社長、右が本田社長兼CEO)
(左が杉原社長、右が本田社長兼CEO) 大手運用会社のアセットマネジメントOneは、米国で確定拠出年金(DC)事業を展開する大手運用会社ティー・ロウ・プライスの日本法人と協働し、退職に向けたリタイアメントビジネスを本格展開する。
第1弾は、ターゲット・イヤー・ファンド(TYF)「未来のわたし」シリーズを新規設定する。想定退職年に向けて、ポートフォリオのリスク性資産の比率を引き下げ、年齢に応じた最適な資産配分で運用してくれる。日本向けに新たに開発した「グライドパス(配分設計)」を使い、アクティブ戦略を含むさまざまな資産クラスを組み込んだ最新の長期分散ポートフォリオで運用する。
さらに両社は、①金融資産全体の把握の簡便化 ②金融経済教育の高度化 ③ライフプランに寄り添った商品の提供-などで協働し、リタイアメントビジネスを進化・発展させる方針だ。
アセットマネジメントOneの杉原規之社長や、ティー・ロウ・プライス・ジャパンの本田直之社長兼CEOらが記者会見し、リタイアメントビジネスの課題や新ビジネスの方向性などを語った。主なポイントは以下の通り。
◆DC加入者に踏み込んだサポートが必要=杉原社長
杉原氏(アセットマネジメントOne社長)=新NISA導入に続いて、企業型DC(確定拠出年金)や個人型DC(イデコ、iDeCo)の制度改革が進められている。拠出期間の延長、掛け金の増額、加入者のための運用の「見える化」などが議論されており、個人の資産形成の環境は大きく変わろうとしている。
一方で、わが国の年金制度やリタイアメント・プランニングに対する理解度には、依然として課題がある。元本確保型商品で運用している加入者が約2割いて、インフレが常態化する社会においても十分な資産形成に取り組めていない。また、投資性商品を選択しているDC加入者においてもマーケットの動きに合わせて短期的な売買を行う動きも一部に見られる。このため、DC加入者により踏み込んだサポートが必要だ。
当社は、米国でリタイアメントビジネスをリードしてきたティー・ロウ・プライスと共に、現役世代から退職後に向けた資産形成の領域で協働し、今般、新たなTYF「未来のわたし」シリーズの新規設定が実現した。
ティー・ロウ・プライスは、TYFの先駆者であり、20年以上の運営の歴史を持つ。新規設定する「未来のわたし」シリーズは、日本の経済環境や社会保障制度を考慮した、日本独自のグライドパス(年齢に応じて調整する資産配分)を設計し、加入者が運用をファンドにまかせたままで、適切な資産形成ができることを目指している。
先行する米国で豊富な経験を持つティー・ロウ・プライス社と、リタイアメントビジネスを推進することで、資産運用業界全体に好循環をもたらしたい。今回のターゲット・イヤー・ファンドの共同開発が、その起点になればと願っている。
◆現在から未来へ分散したポートフォリオを提供=本田社長兼CEO
本田氏(ティー・ロウ・プライス・ジャパン社長兼CEO)=アセットマネジメントOneが新規設定するTYF「未来のわたし」シリーズで、当社はグライドパスの設計と資産配分に関する運用助言を行う。
TYFは、個人を取り巻く現在から未来への状況をしっかり考慮した上で、丁寧に商品を形成している。ターゲットに設定した年まで、個人の金融資産を長期的に分散したポートフォリオに自動で導いていく、利便性の高い商品だ。
ティー・ロウ・プライスは、個人の老後に向けた資産形成を支援するリタイアメントビジネスに取り組んで、40年の歴史を持つ。世界のお客さまからお預かりする約250兆円の資産の3分の2をリタイアメントビジネスが占めている。
また、当社は、米国でDCの運営管理業務を行い、約230万人のDC加入者の資産管理を行っている。そこでは、単に運用商品を提供するだけでなく、加入者用のエンゲージメント・ツールを開発し、教育活動にも取り組んでいる。
日本では、アセットマネジメントOneや年金シニアプラン総合研究機構と共に「資産形成を社会実装するための長期研究チーム」で、より良い資産形成の実現に向けて、取り組みを推進している。国民一人ひとりの資産形成を支援し、豊かな未来を実現する画期的な運用ソリューションを、アセットマネジメントOneと協働で提供できることを、うれしく思っている。
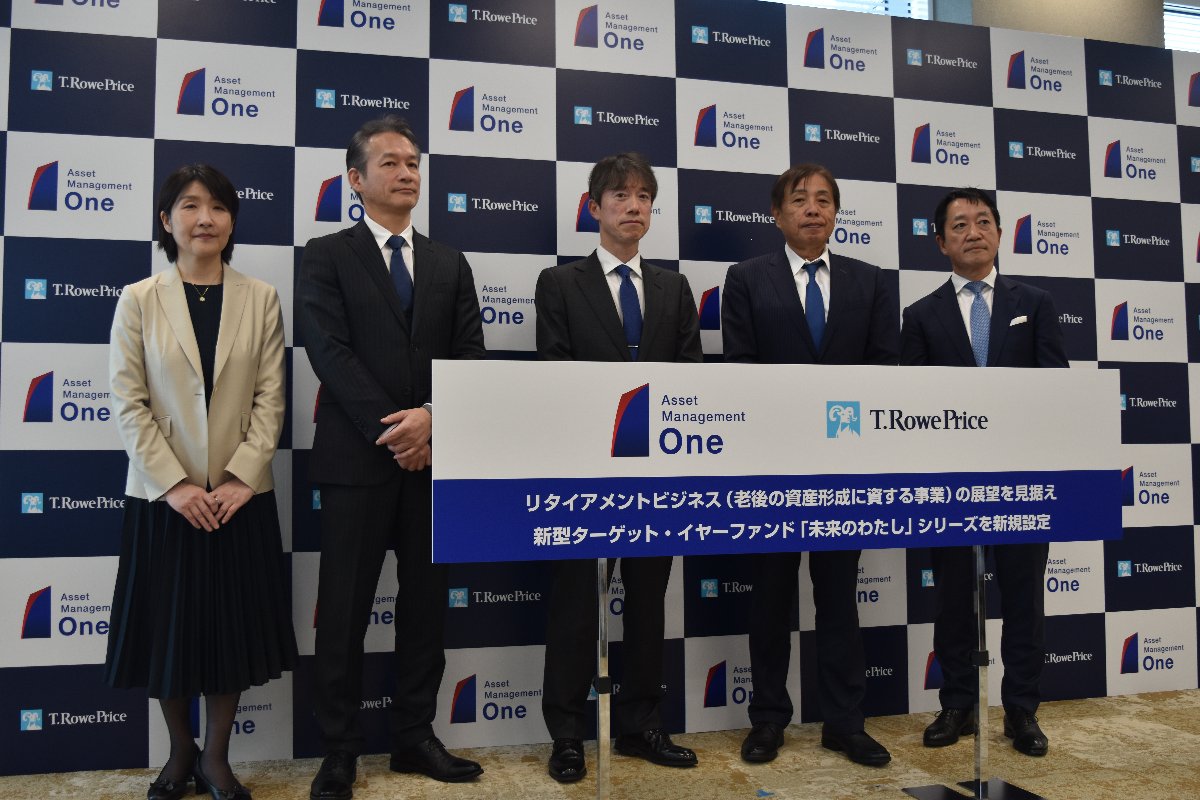 (左から、伊藤氏、三木氏、杉原氏、本田氏、宮島氏)
(左から、伊藤氏、三木氏、杉原氏、本田氏、宮島氏)
◆新しい金融経済教育、パーソナライズされた情報が重要=伊藤氏
伊藤雅子氏(アセットマネジメントOne執行役員 企画本部副本部長 兼 未来をはぐくむ研究所長)=「アセットマネジメントOne 未来をはぐくむ研究所」は、「個人の資産形成や金融経済教育の分野における啓発・普及活動を加速させること」をミッションに掲げ、商品とは切り離した中立客観的な立場で、情報提供を行っている。
昨年は、年金シニアプラン総合研究機構およびティー・ロウ・プライス・ジャパンと共に外部有識者を加えた研究チームを立ち上げ、DC加入者の日米比較を行った。分析結果を3点共有したい。
1点目は「教育ツールの内容」だ。米国は日本よりも多様な種類のツールを提供し、従業員の資産形成を支援している。例えば、資産形成の目標の設定や管理方法、証券口座や銀行預金と一括管理できるサービスなど、パーソナライズされた情報が提供されている。日本では、汎用(はんよう)的な教育ビデオや資料が中心だ。
2点目は「加入者の評価」だ。米国では、会社や運営管理機関が提供する教育ツールやコンテンツについて、「非常に役に立つ」と高く評価する人が34%もいる。日本は12%にとどまった。
3点目は「日米の加入者の情報源」だ。米国の加入者は、運営機関や会社が提供するツールやコンテンツを信頼して活用している。一方、日本は、各種メディアやSNSを利用し、自助努力で対応している人が多い。
DCやiDeCoなどの退職給付制度は、加入すれば半強制的に積み立てが開始され、基本的には中断することなく、中長期で効率的な資産運用が行われる。個人ではなかなかできない合理的な行動を、制度が代わってやってくれる。このため、「いかに正しい知識で初期設定するか」がとても重要になる。
◆DCファンドへ資金流入拡大、短期売買する加入者も-三木氏
三木威氏(アセットマネジメントOne常務執行役員 機関投資家フィデューシャリー・マネジメント本部長)=DCを取り巻く環境が大きく変化している。1点目は、新NISAの開始が契機になり、DCへの資金流入額が大幅に増加していることだ。具体的には、2024年のDC専用ファンドの資金流入額は1兆0262億円となり、過去5年平均(2019-23年)の1.5倍に拡大した。海外株式ファンドに絞ると資金流入額は2.4倍になっている。
2点目は、加入者の運用スタイルに変化が見られることだ。DCにおいて、比較的短期に売買を繰り返す加入者も存在すると思われる。株価が下落するとファンドに資金が流入し、株価が上昇するとファンドから資金が流出する傾向が見られる。
DC加入者の課題として、①年金制度や金融経済の知識不足 ②若年層を中心にSNSが情報源になっている ③加入者の就労形態により情報へのアクセス機会に差があり、コンテンツを十分に届けられていない可能性がある-などが浮上している。DCに無関心な加入者も存在しており、改めて金融経済教育の重要性を認識している。
ティー・ロウ・プライスは、日本の20年先を走る米国の資産運用業界の最先端で活躍している運用会社だ。同社とタッグを組み、知見を共有することで、この20年の差を短縮して、最新のサービスを日本で提供していきたい。
◆TYDと金融経済教育は両輪=ティー・ロウ・プライス・ジャパンの宮島氏
宮島靖郎氏(ティー・ロウ・プライス・ジャパン取締役 機関投資家ビジネス統括責任者)=米国では、日本と異なり、TYFが圧倒的に普及している。デフォルトファンド(運用指定方法)の91%がTYFで、最も人気の商品になっている。「TYFは、運用をおまかせできるから、金融経済教育がおろそかになるのではないか」と懸念する声もあるが、米国では金融経済教育とTYFがリンクして高め合っている。
当社は2019年からプロジェクトチームを立ち上げ、日本におけるTYFの課題を調査研究してきた。退職直前に得ている手取り額に対して、退職後の収入が大きく減ると幸福感が薄れてしまう。当社は、40年後の勤労者の姿を雇用条件や社会保障制度の中でイメージして、「生身の人間を金融面から支援すること」を目標として、さまざまな商品・サービスや、運営管理機関のツールを開発してきた。
今回のTYFのグライドパスの策定に当たっては、今後80年の経済シナリオについて約1万通りのモデルを生成し、日本のDC加入者の給与、実質生活費、公的年金等のモデルを加えて、加入者の満足度を最大化するものを目指した。
新ファンドは、11の資産クラスを使い、アクティブとパッシブの20戦略を組み込んだ。ここまでの分散ポートフォリオを提供するファンドは、米国でもそれほど多くない。米国と日本の差を20年間ワープして、米国の最先端の運用商品を日本の勤労者の方々に提供できる。



![オペレーションF[フォース]](https://financial.jiji.com/long_investment/img/opf_banner.jpg)