三菱UFJアセット、7人のチームリーダーが記者会見=「チーム制」でアクティブ運用を強化
2025年04月04日 10時30分
三菱UFJアセットマネジメントは、アクティブ運用の主力戦略に「チーム制」を導入した。チームリーダーに運用や制度面の権限や裁量を移譲し、独立したビジネスユニットとして活動することで、運用エンジンの強化と体制の堅確化を図る。7人のチームリーダーが記者会見し、各戦略の運用哲学や特徴などを説明した。主なポイントは以下の通り。(4月1日現在の肩書を使用しています)
◆アクティブ・アロケーション・チーム

石金淳氏(戦略運用部エグゼクティブファンドマネジャー)=国内外の株式や債券等に分散投資しつつ、相場観に基づいてアクティブに比重を変更する運用を行っている。上昇すると判断した資産のウエートを高めたり、下落すると判断した資産を減らしたりすることで、超過収益を着実に積み上げ、低リスクで効率の高い運用を目指している。
アクティブアロケーション運用において明白な成果を上げるには、相場観の鍛錬とともに機敏な投資行動が不可欠だと考えている。相場の予測に際しては、相場水準の予測は実際かなり困難とみており、それよりも相場の方向性を的中させることに力を注ぐことが肝要だ。
そのためには、トレンドの持続時間を推察しつつ相場の転換点を追求することに力を注ぎ、機動的なアロケーション変更によって実現益を積み上げ、運用成績の向上、および好成績の維持を図っていく考えだ。
相場局面を判断するために「株価トレンド」「政策金利」「市場リスク」の三つの定量分析を参考にしているが、「いつ売買するか」については、それぞれの定量分析が持つクセを読みつつ、ファンドマネジャーが機動的に定性判断しており、運用力のカギになっている。
◆日本株グロース戦略

小島直人氏(株式運用部エグゼクティブファンドマネジャー)=長い目で見ると、企業が生み出す付加価値が向上すれば、企業価値は比例して高まる。成長株投資のアップサイドのポテンシャルには天井がない。徹底的なリサーチでダイヤの原石を探し出し、株価がダイヤの持つ本来の価値に達するまでしっかりと保有し続けることが、グロース株投資の魅力であり、われわれの一丁目一番地だ。
われわれの投資哲学は、将来の成長をもたらす、潜在的な高い「本源価値」を有する企業に厳選投資することだ。こうした企業を見つけ出すために、五つの定性的視点とメガトレンドというフレームワークを使っている。
五つの定性的視点は「市場成長力」「企業成長力」「競争優位性」「収益性」「マネジメント力」だ。メガトレンドは、「将来的に不可避と考える社会構造の大きな変化」だ。「脱炭素社会」「デジタル化」「人口の高齢化」により社会が変化する過程で、さまざまな成長産業が生まれ、人々の生活をより豊かにする。
ヨットに例えると、良い風が長く吹くルートを探知し、その海域にマッチしたヨットと、その海域を熟知した腕の良いヨットマンを見つけることができれば、良いパフォーマンスを上げる近道になるし、成功の確率が上がるだろう。
われわれは、6人のメンバー全員で業種を分担してボトムアップリサーチを行っている。それと並行して、それぞれが知見を持っている電気自動車、人工知能(AI)など10個以上の成長市場と技術分析を行っている。
企業への面談、現地施設訪問や取材をはじめさまざまな調査を行うことで、「本源価値はどれくらいの水準なのか」「本源価値は果たして本当に実現するのか」を見極めることをミッションとしている。
◆日本株コアバリュー戦略

畑澤巧氏(株式運用部エグゼクティブファンドマネジャー)=低PBR(株価純資産倍率)に注目するトラディショナルなバリュー株(割安株)投資とは異なり、「当チームが考える『真の企業価値』と市場価格のギャップ」を割安度と定義して投資を行っている。
各企業の経営戦略によって生じている、もしくは将来生じるであろう収益構造の変化を丹念に分析し、業績とバリュエーションの両面から「市場が気づいていないギャップ」を見つけている。
われわれの運用戦略は「株価が安いものには安い意味があり、高いものには高い意味が」という考え方が入り口になっている。「現在の株価が何を表しているか」を深く考えることから、われわれの投資はスタートする。仮に、市場が考えるバリュエーションやEPS(一株あたり純利益)に対して、われわれの予想がそれを引き延ばすものであれば、それがわれわれの考える「真の企業価値」であり、市場の株価とのギャップが超過収益の源泉になる。
セクターに精通した担当者が業界動向や企業ごとの事業環境を基に独自の業績予想を作成した「ファンダメンタルズアプローチ」をベースに、独自の「マネジメントアプローチ」で優れたマネジメント力の企業を発掘し、企業価値のボトルネック解消や評価改善に向けて積極的な変化を促す、長期にわたるエンゲージメント(投資家と企業の対話)を実施している。2024年は、年間2000件を超える企業取材を実施し、71件の対話を行った。
◆日本株オポチュニティ戦略

友利啓明氏(株式運用部エグゼクティブファンドマネジャー)=この戦略は、例えばバリュー・グロースといった運用スタイルや、大型株・中小型株といったサイズに捕らわれることなく、アルファー(超過収益)を追求していく。
一つ目の着眼点として、「企業価値を大きく動かす変化」に注目し、変化について「①顕在化待ち」「②顕在化」「③織り込み完了」というようにステータス管理を行って、市場にどれだけ織り込まれているかを適切に把握しながら、「一歩先んじた投資」を行っている。
二つ目の着眼点は、「競争力のある優良企業であるか」だ。企業価値向上の実現の前提となる「事業基盤」「財務基盤」「マネジメントクォリティー」「シエア」を有する企業を「競争力のある優良企業」と定義し、35~50銘柄に厳選投資している。
当チームのメンバーは3人で、オポチュニティを逃さないため、網羅的なリサーチを行っている。私は、証券会社のアナリストが毎日発信する400~500本のレポートを読み、外国株の決算をチェックしており、大型株を中心に全セクターをカバーしている。他の2人はそれぞれ、マクロ経済と新規公開企業、中小型株中心に全セクターの開示情報のチェックを担当している。
◆海外株グロース戦略

西直人氏(株式運用部エグゼクティブファンドマネジャー)=私は、アジア株をはじめとする、さまざまな外国株を15年ほど見てきた。一貫して直接現地に取材して、ワン・オン・ワンのミーティングを行い、中長期の目線で銘柄を評価してきた。当チームは、こうした哲学を基づいて毎日ミーティングを行い、約3000億円の資金を運用している。
チームの個別銘柄選定の考え方だが、「株価は、企業業績を適切に反映するが、実現までに時間がかかることが多く、さらに、長期の業績成長の持続性まで反映しないことが少なくない」という観点に立っており、「『長期目線で業績を評価し、長期間保有する』という投資スタイルによって、超過収益の獲得が可能になる」と考えている。
なぜ、長期投資が良い結果を生むのだろうか。一般的なアナリストの業績予想は、今年、来年といった短い期間で行われることが多い。5年後、6年後といった長期の予想は、ほとんど行われていない。このため、企業の中長期の業績にフォーカスすることで、投資機会があると考えている。
「株価は利益に応じて上がっていく」と考えると、良い株を見つけ、長い目でみれば株価は上昇していく。ただ、短期的にはブレがある。そこは、ある程度許容して、利益成長の大きな幹の部分を取っていく運用方針だ。
銘柄選定に当たっては「業界(市場)の規模・成長性」「競争力」「ビジネスモデル・成長戦略」の3点を重視している。中長期に銘柄を保有する観点では、こうしたベーシックなポイントが、より重要になってくる。
「日本の運用会社が外国株を扱うのは不利ではないか?」とよく聞かれるが、中長期の視点で企業を評価する、われわれのストラテジーにおいては、日本にいることがポジティブに働いている。米国など海外の株式市場を離れたところから見ることで、日々の短期の視点のニュースやノイズから離れることができるためだ。
◆円債総合戦略チーム
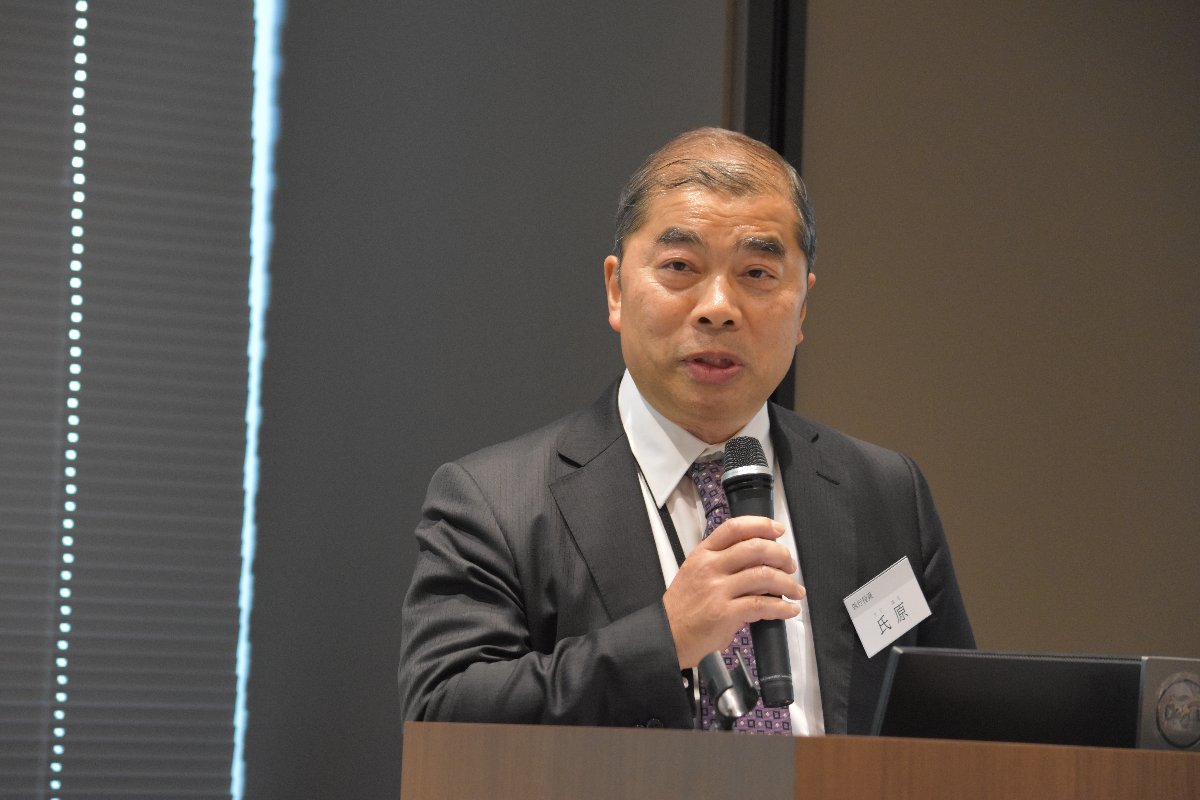
氏原圭作氏(エグゼクティブフェロー)=当チームでは「国内債券総合戦略型運用」をメインの商品にしており、日本の債券市場インデックス(野村ボンドパフォーマンスインデックス)をベンチマークとして、独自の金利戦略とクレジット戦略をもとに超過収益を獲得するアクティブ運用を行っている。公的年金や企業年金を主要顧客としている。
この戦略の特徴は、3点ある。①金利予測に依存せず、債券市場の定量的分析をベースに投資する ②ロスカットポイントを明確にしつつ、メリハリのあるリスクを取る ③事前に定めた判断基準に従った投資行動を取ることで、心理的なバイアス(偏り)による判断の誤りを除外する-だ。
将来の金利水準の予測を当て続けることは大変難しいことだと考えている。また、金利水準、ポジションの損益、良いニュース・悪いニュース等のさまざまな情報が心理的なバイアスを生み、そのバイアスが投資判断をゆがめる要因になる。このため、心理的なバイアスを極力排除し「規律を持った運用」ができるよう、運用のフレームアークを作ることが重要だ。
当戦略では、運用プロセスの中に、定量的判断ツールやロスカットの仕組みを取り入れており、心理的なバイアスに左右されない運用を行っている。
◆グローバル債券戦略チーム

舩津大輔氏(債券運用第二部 債券グループエグゼクティブファンドマネジャー)=当チームは、「海外債券アクティブマザーファンド」を運用している。ベンチマークは「FTSE世界国債インデックス(除く日本・円ベース)」で、わが国を除く世界主要国の公社債を主要投資対象としている。国債以外の債券は、格付けをA格以上とし、組入れ比率の上限もポートフォリオの25%にとどめることで、信用リスクを押さえた、国債中心の運用を行っている。
債券は、株式と違って価格が大きく変動するものではなく、例えば5年後、10年後の償還時に元本が返ってくる。その間、利息が付く。特に国債はデフォルトリスクも低く、マクロ経済ファンダメンタルズを反映して変動していく。
当チームは、景気を定量的に分析して「今どういった景気の状況にいるのか」「今後はどういう状況になるのか」を考え、「そうした時に金利や為替マーケットは、過去にどのように動く傾向があったか」を分析しながら、運用している。
ポートフォリオの構築に当たっては「カントリーアロケーション(為替)戦略」「デュレーション・イールドカーブ(金利)戦略」「利回り較差(スプレッド)戦略」など、収益源泉別の分析体制を最大限活用し、戦略やリスクを分散しつつ作成している。



![オペレーションF[フォース]](https://financial.jiji.com/long_investment/img/opf_banner.jpg)