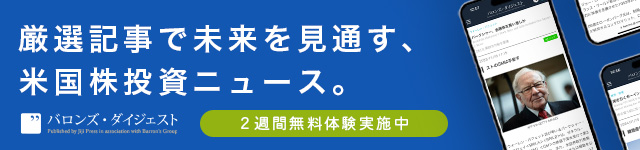サンプル(過去記事より)
世代が分けるお金の使い方と遺し方
死ぬまでは自分で使いたいベビーブーマー世代
若い世代は生きているうちに子どもに使いたい

ファイナンシャルアドバイザーのパティ・ブラック氏の顧客で自営業を営む36歳の男性は、3歳と6歳になる自分の子どもの雇用主だ。事業はハンドメイド品の製作で、子どもたちは商品の掲載写真に登場する。
アラバマ州バーミンガムでサヴァン・ウェルス・マネジメントに勤めるブラック氏によれば、子どもたちは収入を得ているが未成年であるので、父親である男性が子どもに代わってロス個人退職勘定(IRA)(年金制度の一つ。運用・給付が非課税となる)の拠出金を支払うことができるのだと言う。ブラック氏は「早くから貯蓄と投資の重要性を両親から叩き込まれたこの男性は、自分の子にも同じようにしてあげたいと考えている」と説明する。
生きているうちにお金を次の世代に譲り渡すことは、比較的若い世代にとっては身近な選択肢になってきているが、シニア世代にとってはそうではない。米ネット証券大手チャールズ・シュワブが100万ドル以上の資産を持つ人を対象に行った最近の調査によると、27歳から58歳の富裕層は、59歳から76歳の富裕層に比べて、生きている間に次の世代に財産を分け与えたいと答える傾向が2倍を超える。後者のグループは、生きている間は自分のためにお金を使って楽しみたいと答える傾向が強い。
ファイナンシャルアドバイザーは口をそろえて、これは単にある世代が他の世代より気前がいいという問題ではなく、過去の一連の金融危機が今のシニア世代に全てを失うことへの恐怖を植え付け、その一方で物価高は若い世代に自分の子どもの将来への不安を与えていると指摘する。
起こり得る苦難への不安
キャピタル・インテリジェンス・アソシエイツの共同創業者でファイナンシャルアドバイザーのミッチェル・クラウス氏によれば、シニア世代は大恐慌を直接見聞きした世代であり、コツコツと貯めたお金を全て失うことも含めて、どんなことも起こり得るのだと考える世代だと言う。彼らの相続に対する考え方は、万が一その不安が現実のものとなった場合に備えて、生きている間は持っているものを手放さないというものだ。
クラウス氏の顧客の一人に1000万ドルを超える資産を保有する90代の女性がいる。その女性と亡き夫は子どもたちが家を購入する援助をしたいと考えていたが、住宅ローンのための資金を子どもに与えるのではなく、貸すことを選んだ。クラウス氏は「第二次世界大戦の世代である彼らは、いつか自分たちのお金が底をつくのではないかと本当に心配していたのだ」と説明する。
お金の話をタブーと捉えるか否かという世代間の考え方の違いも、この傾向に一役買っている。フィデリティ・インベストメンツの最近の調査では、米国人の半数以上が親とお金の話をしたことがないと答えているが、状況は変わりつつある。5人のうち4人がかつてタブーであったお金の話を若い世代とすることが大切だと答えている。
クラウス氏には昔ながらのタブーを体現する顧客がもう一人いる。一家の女主人であるその女性が保有する純資産は1200万ドルで、成人した2人の娘のための資産を別に分けておいたものの、そのことを秘密にしていた。クラウス氏によれば、守れないかもしれない約束はしたくないし、金銭的な話題には触れないということに慣れているからだと言う。
しかし女主人の最初の孫娘が最近、大学に進学すると、女主人が4万ドルを負担することを申し出て、その孫娘の母親である女主人の娘を驚かせた。クラウス氏は「孫娘の両親は何年も苦労して大学のための資金を貯めたのに、その苦労は無用だったことを知ったのだ。私は一家のファイナンシャルアドバイザーの立場から、娘(孫娘の母)には、他の顧客に通常助言するよりも少ない額を用意するよう助言していたが、4万ドルはもう既に用意があるということを伝えていい立場にはなかった」と語る。
「苦しい時代」で分かれるアプローチ
長年、所得から貯蓄を捻出していた人にとっては支出が所得を上回る生活へのシフトもハードルが高いようだ。フロリダ州スチュアートを拠点とするHBKSウェルスのファイナンシャルアドバイザー、マイケル・ロフリー氏は、「われわれの顧客の多くは長年、コツコツと貯蓄や投資を継続して億万長者にまでなっており、こういうタイプの人にとって退職したからと言って古い習慣を変えることは難しい」と指摘する。
一方でクラウス氏は、X世代(1965~1980年生まれ)や、特に物価高騰の中で育ったミレニアル世代(1981~1996年生まれ)は、社会で順調なスタートを切ることがいかに難しいかを目の当たりにしているため、異なるアプローチを取る傾向にあると言う。
例えば、住宅購入はかつてないほど困難で、米国勢調査局のデータによれば、住宅の販売価格の中央値は、2000年の16万9000ドルから昨年12月には42万7000ドルに跳ね上がっている。2000年に平均3501ドルだった公立大学の年間の授業料等も2022年度は9750ドルだ(エデュケーション・データ・イニシアチブ調べ)。若い世代は不況やパンデミック(感染症の世界的大流行)を何とかやり過ごす中で、経済が破綻することへの恐れに対する耐性はシニア世代より強いようだ。
クラウス氏は「彼らにとっては、お金が底をつくことより、子どものアメリカン・ドリーム実現のための戦いをいかに支援できるかが心配なのだ」と語る。たとえその戦いがブラック氏の顧客のようにおむつがまだ取れない幼少期に始まるのだとしても。