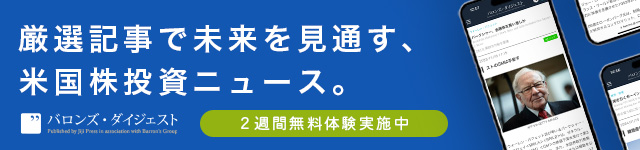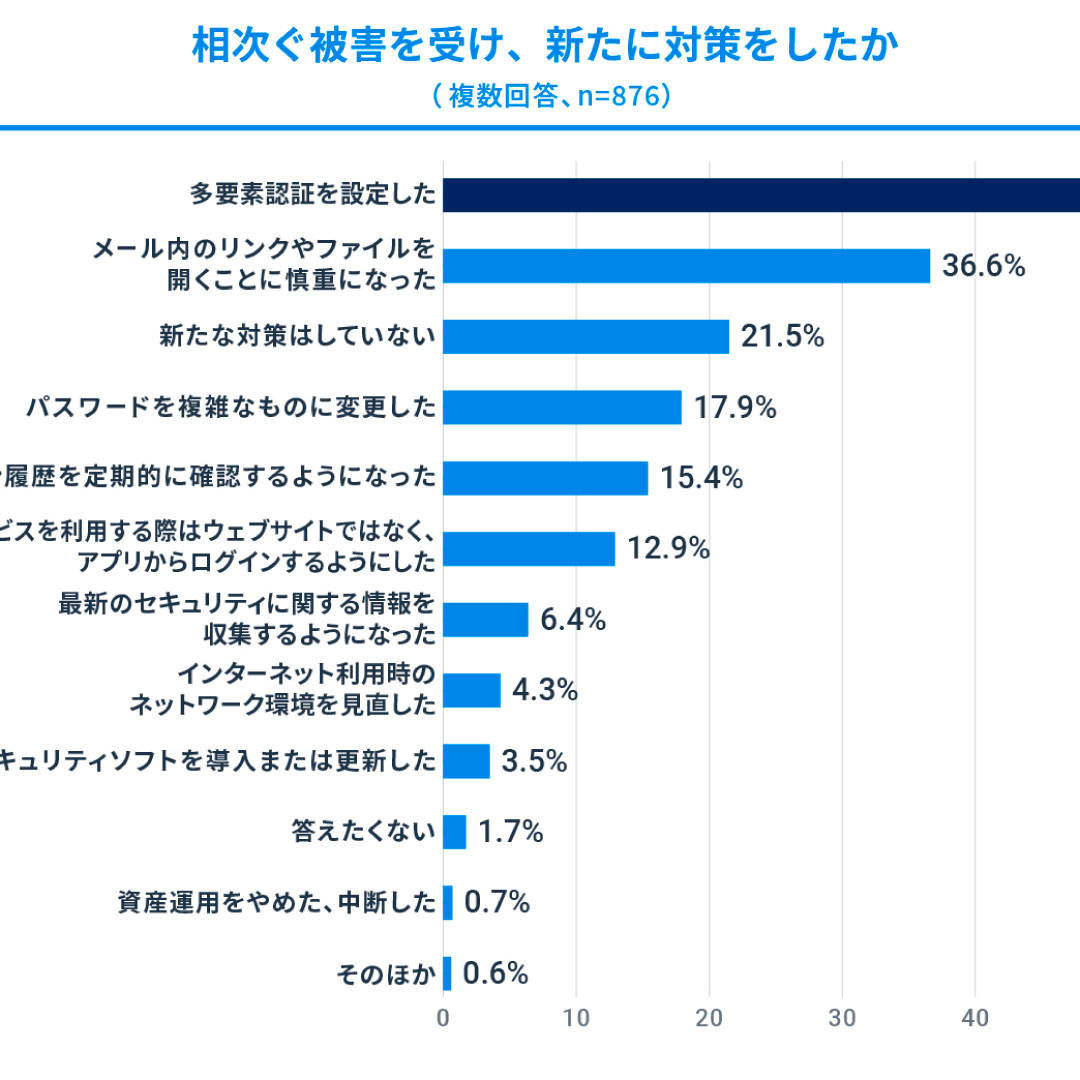サンプル(過去記事より)
米国株動揺時の投資先候補
暴落の可能性に対するヘッジ方法は
暴落は前触れもなくやってくる

S&P500指数は2月19日の高値から10%超下落している。単なる不安定さなのか、それとも何らかの警鐘なのか、それは誰にも分からない。それが株式投資に伴う素晴らしくも恐ろしいリスク・リターンの本質だ。一般の節約家にとって、株式のように長期にわたり富を増やすことができる手段は、ほとんどない。金融大手UBSによると、米株式市場の1900年以降のリターンは年率9.7%だ。これに対し、債券は4.6%、米国債は3.4%、そしてインフレ率は2.9%だった。しかし、株式相場は前触れもなく20%、さらには50%を超える下落に見舞われる可能性があることも歴史が示している。そして、数年で相場が回復する場合もあれば、10年以上かかる場合もある。
今、何が株式相場を押し下げている要因なのかさえ分からない。トランプ大統領が主要貿易相手国に対していきなり関税砲を放ったことで、投資家は、株式市場が動揺するような問題についてはトランプ氏も慎重に事を進めるはずだという想定を再考せざるを得なくなった、という話に聞き覚えがあるかもしれない。そうなのかもしれない。しかし一方で、日本が1月に2008年以来の水準まで利上げを実施したことで、大手トレーダーにとって米ハイテク株の安価な購入資金調達源の一つが魅力を失った、あるいは、2025年予想株価収益率(PER)が20.5倍に達した米国株が単に割高だということなのかもしれない。
金融大手ドイツ銀行の最近のリポートは、現在の状況が2000年のITバブル崩壊の初期段階に似ているとしている。ハイテク株が急落する一方で、ディフェンシブセクターの株価は上昇している。2000年当時、S&P500指数は年末までに10%下げただけだったが、その後弱気な見方が拡大し、翌年は13%、翌々年は23%の下落となった。恐ろしい話だが、この10年間、暴落に関する警告は幾つもあったし、実際の暴落もコロナ禍で1度経験した。それでも、S&P500指数は暴落後、コロナ禍中に215%のリターンを上げている。
だから、株式をまとめて投げ売りするようなことをしてはいけない。もし不安なら、暴落リスクのヘッジ方法を検討すべきだ。多くのお粗末なヘッジ方法と、ごく少数の優れたヘッジ方法がある。以下、最悪の方法から最善の方法まで、幾つかを紹介する。
インバース型上場投資信託

一切検討すべきではない。トレーダー向けで、長期投資家向けではない。長期投資家の最強の味方である「複利効果」を敵に回すのがこれらの上場投資信託(ETF)だ。デリバティブ証券を使用して一日単位で相場とは逆の方向に賭ける。1日よりも長い期間にわたって、相場の動きを正確に相殺することはできない。通常は手数料も高い。ディレクション・デイリーS&P500ベア3XシェアーズETF<SPXS>は年間1.02%だ。価格は年初来で21%上昇しているが、過去10年間では99%下落している。価格がセント単位まで下落しないように、定期的に株式併合を実施している。
オプション
単一銘柄あるいは株価指数に対するプットオプションを購入し、下落に備えることも可能だ。比較的高リスクだ(急速に価値を失い、無価値のまま行使期限を迎える可能性がある)が、損失はプットの購入価格に限定される。保有株式を原資産とするカバード・コールオプションを売り建てすることもできる。プット購入よりリスクは低い。オプション料を前受けできる一方で、株価が上昇した場合のキャピタルゲインを手放すことになる。カバード・コールを売ると同時に、そのオプション料収入でプットを購入する投資家もいる。
一つの問題は、相場が急落した場合、伝統的な株式投資家であれば相場がいずれ回復するまで待つことができるが、オプションには時間的価値というものがあり、行使期限に向けて減少を続けるため、長くは待てないことだ。2022年、S&P500指数は19.4%下落したが、突然暴落するのではなく、年間を通じて上下を繰り返しながら下落した。投資銀行RBCキャピタル・マーケッツのデリバティブ戦略責任者、エイミー・ウー・シルバーマン氏によれば、典型的なオプションヘッジ戦略を使用した投資家は、市場の下落と同程度の損失を被ったという。
現金比率の引き上げ
金額や期間にもよる。相場が下落する時期を知るのは不可能であり、株価は下落するよりも上昇する傾向にあるため、タイミングを誤る可能性が高い。そして、頑固になり、間違ったのではなく早過ぎただけだと判断し、そして絶望し、失敗を認めて買い戻す頃には、株価ははるかに高くなっている。幸運に恵まれる場合もあるが、運試しは長年の貯蓄ではなく、全米大学バスケットボールの勝敗予想くらいにしておいた方がいい。ただし、緊急時に備え、十分な現金を準備しておくべきだ。
「安全」銘柄
間違いではないが、問題は安全な銘柄の見極めだ。リスクはリターンと関連しているというのが現代の投資原則の一つだが、リスクを個別銘柄レベルで満足に計測できる方法は発見されていない。ベータ値と呼ばれるリスク指標(通常は、過去5年程度のS&P500指数に対する相対的なボラティリティー)を記載した株価情報をオンラインで検索可能だが、本当に知りたいのは将来のボラティリティーであり、誰にも分からない。
ディフェンシブとされている銘柄にも注意が必要だ。この数週間、市場が低迷する中、加工食品メーカーと電力会社の株価は上昇している。しかし、食品大手は売上高の減少に苦しんでいる。若い消費者の健康志向や高齢者の肥満治療薬の影響なのか、単にインフレと家計の逼迫(ひっぱく)によるものなのか、原因は分からない。電力会社はデータセンター向けの電力需要を受け好調だ。しかし、ユーティリティー・セレクト・セクターSPDR ETF<XLU>はこの1年間で21%上昇しており(S&P500指数は8%)、PERは18倍だ。ディフェンシブなバリュエーションと言えるのだろうか。
ディフェンシブ株であれ、景気敏感株であれ、バリュエーションが適切で、債務残高がコントロール可能な水準にあり、信頼性の高い増加基調にあるキャッシュフローを持つ、経営の優れた企業を探すのが賢明だ。
S&P500均等加重指数
趣旨は理解できる。時価総額で加重しないことにより、株価が大幅に上昇した銘柄への配分が減り、上昇していない銘柄への配分が増える。昨年末時点で、ITセクターのウエートがインベスコS&P500イコール・ウエートETF<RSP>では14%だったのに対し、SPDR S&P500 ETFトラスト<SPY>では32%だった。最近では均等加重ファンドの方が好調だ。ただ、これは少し奇妙で恣意(しい)的な考え方だ。ハイテク銘柄はもっと重要ではないのか。電力会社は小規模な企業が多く、電話会社は数が少なく大企業だというだけで、時価総額ベースの比率をこれほど大きく上回るウエートで電力会社に配分し、通信会社のウエートをこれほど引き下げるべきだろうか。なぜ、時価総額ベースで市場の2%にすぎない不動産投資信託(REIT)への配分を6%にするのだろう。残る98%の企業も不動産を保有しているではないか。間接的に狙っているもの、すなわちバリューに投資すべきだ。
バリュー株
バリュー株は長期的にはグロース株よりも優れたパフォーマンスを上げると考えられている。最長期間ではその通りの結果となっている。1926年に投資した1ドルは、バリュー株の場合は現在13万1534ドルになっているが、グロース株の場合は1万1744ドルだ(ダートマス大学のケネス・フレンチ教授がまとめたデータを使用し、UBSが報告した株価純資産倍率=PBR=に基づいている)。しかし、ここ数十年の結果は違っている。1990年代初頭以降、S&P500グロース指数はS&P500バリュー指数を引き離している。これが何を意味するのかは分からない。しかし、バリュー寄りの均等加重ファンドの一部組み入れを考えているのであれば、インベスコFTSE RAFI米国1000 ETF<PRF>のような、より直接的なアプローチを検討すべきだ。このファンドは、純資産、キャッシュフロー、売上高、配当によって企業のウエート付けを行っており、今年も過去10年間も、均等加重ファンドよりわずかながら優れたパフォーマンスを上げている。
外国株
是非検討すべきだ。ほぼ過去半世紀の間、米国の投資家が国際分散によるリスク低減という助言に従った場合、リターンもボラティリティーも残念な結果に終わっている。しかし、欧州も日本も割安に見え、両市場とも最近活気を取り戻している。iシェアーズMSCIジャパンETF<EWJ>は年初来で4%、iシェアーズ・コアMSCIヨーロッパETF<IEUR>は13%上昇している。これに対し、SPDR S&P500 ETFトラストは5%下落している。これをもって、待ちに待った反発の始まりと呼ぶのは躊躇(ちゅうちょ)されるが、その可能性はある。日本は世界の株式市場の6%、欧州はその約2倍を占めている。配分の参考にしてほしい。
今年、日本や欧州を上回る上昇を示しているのが中国だ。重要な市場だが、国家の統制下にあり、外国人投資家の所有権には疑問が付きまとう。長期リターンは低調で、1990年代までしか遡れない。しかし、中国本土は世界の株式市場の3%を占めている。iシェアーズMSCIチャイナETF<MCHI>経由でアクセス可能だ。米国のウエートが65%しかないことを許容できるのであれば、バンガード・トータル・ワールド・ストックETF<VT>も選択肢だ。
債券
いよいよ本題だ。冒頭で言及したとおり、長期リターンは平凡だが、インフレ率を上回っている。ただし、数十年にわたりインフレ率を下回った時期がある。しかし真の魅力は、通常、株式との相関性が低いことだ。株価暴落の影響から免れることはできないが、有力な緩衝材となり得る。さらに、過去10年間の株式相場の上昇を考えれば、債券への配分を増やす必要があるかもしれない。パッシブなエクスポージャー取得の手段としては、シュワブ米国総合債券ETF<SCHZ>がある。コストはほぼゼロ、利回りは4.4%、平均デュレーションは6年弱だ。自分自身でエクスポージャーを組み立てたい場合、シュワブの債券ストラテジスト、コリン・マーティン氏が好むのは、利回り4.5〜5.5%の高格付社債とインフレ指数連動国債(TIPS)だ。TIPS債の中には、インフレ調整前利回りが20年間のレンジ上限に近い2%のものもある。