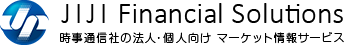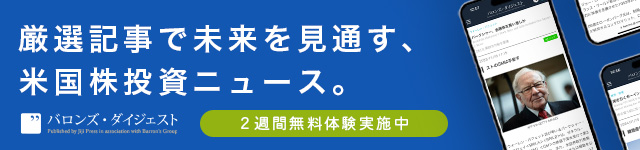サンプル(過去記事より)
ITバブル崩壊から25年、次はAIバブルが崩壊か
マクロ環境は異なっても、景気サイクルの流れはいつも同じ
現在のAIへの熱狂と25年前のITバブルとの類似性

25周年というものは通常、喜ばしい節目だ。しかし、ベテラン投資家にとって今回の25周年はほろ苦いものとなっている。今から四半世紀前、熱狂に包まれたインターネットの強気相場はピークを迎え、苦痛を伴う弱気相場へと突入した。そして、米経済を10年以上続いた景気拡大からリセッションへと引きずり込んだ。
ダウ工業株30種平均(NYダウ)が当時のピークを迎えたのは2000年1月で、S&P500指数とナスダック総合指数は2カ月後の3月にピークを記録した。本誌2000年3月20日号に歴史的なカバーストーリーが掲載されたのは、後者二つのピークの間だった。ドットコム業界の神童たちが、根拠なき熱狂に駆られた投資家(より正確に言えば投機家)によって投じられた資金を驚異的なペースで燃やし尽くしているという内容だった。
雑誌のカバーストーリー記事は侮りがたい逆張り指標だ、という皮肉めいた言葉があるが、このときは見事に的中した。数十億ドルがオンライン・ベンチャーに投資されたものの、それらの企業も資金も消えてなくなった。まさに、本誌記事の予見通りの展開となった。
この出来事が、いま強烈なデジャブ(既視感)を呼び起こしている。本誌の元記者であるジェームズ・グラント氏はグラント・インタレスト・レート・オブザーバーの最新号で「ある年代以上の読者なら、2000年前後の光ファイバー・通信業界の崩壊を思い出すだろう。1998年から2002年にかけてのように、現在のテクノロジー企業は過剰な熱狂、過剰発注、そして過剰投資の大きなリスクに直面している」と指摘する。
AIモデル開発とデータセンターへの巨額投資、不透明なリターン
巨額のフリーキャッシュフローを生み出してきた米国の超大型ハイテク株、マグニフィセント・セブン(M7)は、いま人工知能(AI)への投資に数十億ドルをつぎ込んでいる。アンドリュー・ベアリー記者が先週このコラムで指摘したように、メタ<META>(旧フェイスブック)、マイクロソフト<MSFT>、グーグルの親会社アルファベット<GOOGL>の3社だけで、2025年のAI関連投資は2000億ドルに達すると見込まれている。その額は、これらの企業の年間売上高の約4分の1に相当する。しかし、中国のAI開発企業ディープシークが、米国のAI企業に比べわずかなコストでAIモデルを開発できると報じられており、米国例外主義の正当性を揺るがしている。いずれにせよ、米国のテクノロジー大手がAIに投入している数十億ドルの投資が、どれほどのリターンを生むのかは不透明だ。
グラント氏は、政府がAIに全力を注ぎ込んでいることも、特に巨額の資金がデータセンターへの投資に向かっていることも、危険信号の一つだと付け加える。バイデン前政権は、国防総省とエネルギー省に対し、連邦政府の土地をリースし、新たなデータセンター建設の許可手続きを迅速化するよう指示した。トランプ政権もこれを引き継ぐ形で、ソフトバンクグループ<9984>、チャットGPTを開発したオープンAI、法人向けソフトウエア大手のオラクル<ORCL>による1000億〜5000億ドル規模の投資計画、スターゲート・プロジェクトを発表した。2023年初め以降に発表された新規データセンター建設計画の電力需要は、米国の全原子炉94基分の発電量に相当するが、今回のプロジェクトで、さらに電力需要は高まる。グラント氏は、このAIブームの先にある崩壊が、データセンター企業だけでなく、テクノロジー業界全体、さらには信用市場にまで波及する可能性があると警告する。
先月は、かつてネット接続サービス大手だったアメリカ・オンライン(AOL)とメディア大手だったタイム・ワーナーの3500億ドル規模の合併発表から25年という節目でもあった。この合併は、ITバブルのピークを象徴する出来事であり、ビジネス史上、最も株主価値を破壊した合併とも称された。
グラント氏の同僚であるエバン・ローレンツ氏は、イーロン・マスク氏が先週提示した974億ドルのオープンAIに対する買収意向と、かつてのAOLとタイム・ワーナーの合併との類似性を指摘する。ローレンツ氏は、マスク氏が買収提示額を3倍に引き上げる必要があるかもしれないと述べた。なぜなら、ソフトバンクグループによる400億ドルの出資計画が実現すれば、オープンAIの推定企業価値が3000億ドルに達する可能性があるためだ。ローレンツ氏は「経済の最も成長著しい分野でのメガディールは、景気サイクルの底では成立しないことは言うまでもない」と皮肉交じりに付け加えた。
1920年代にもあったバブル
ITバブルとその崩壊以外にも、現在のテクノロジー業界に通じる歴史的な前例がある。通信・放送分野のパイオニアだったラジオ・コーポレーション・オブ・アメリカ(RCA)は、「狂騒の20年代」と言われる1920年代における最も象徴的なテクノロジー株だった。データ会社フィナエオンのチーフエコノミストであるブライアン・テイラー氏は2023年のコラム記事で「1920年代、企業名に『ラジオ』を含めさえすれば、たとえ事業の実態がほとんどなくても株価は急騰した」と記している。RCAの株価は1920年代に200倍に上昇したが、結局、1929年のピークから1932年までに98%暴落した。
複合企業ゼネラル・エレクトリック(GE)は1986年、RCAを1929年の株価を72%上回る価格で買収した。しかし、その間に消費者物価は500%以上上昇しており、1920年代に「ラジオ」として知られたRCA株は、実質ベースでは数十年のスパンで見れば負け組となった。もっとも、ラジオ技術、そしてRCAが開発したテレビ技術は、狂騒の20年代の強気派が想像していた以上の進化を遂げることになった。
マクロ経済状況は異なっても、景気サイクルの流れはいつも同じ
確かに、25年前のマクロ経済環境は現在とは大きく異なっていた。グラント氏は、当時の世界は米国債が不足することを懸念していたと指摘する。当時、米連邦政府の財政は黒字だった。しかし、現在の状況はまるで異なる。中東での二つの戦争、2007~2009年の金融危機、新型コロナウイルスのパンデミック(世界的大流行)、さらには「オバマケア」などの国内政策拡大によって、米政府の財政赤字は戦時を除けば前例のない水準にまで膨らんでいる。
今後、債券市場には米財政赤字の穴埋めのために、多額の国債が供給される見通しだ。米議会予算局(CBO)の予測によれば、今後10年間の財政赤字は年平均約2兆ドルで、これは2025年の国内総生産(GDP)の6.2%に相当する。つまり、今後の資本市場では、AI関連投資と米政府が資金を奪い合うことになる。赤字の主因は、支払い金利(国債の利払い)で、CBOの試算によれば、GDPの3.2%に達している。いわゆる「基礎的財政収支(プライマリーバランス)」の赤字(3.0%)を上回る見込みだ。金利は、経費削減を主目的とする政府効率化省(DOGE)の取り組みでは対処できない領域だ。
グラント氏はインタビューの中で、状況は変わるものの、どの景気サイクルも結果は驚くほど似ていると語った。それでは、25周年おめでとう。