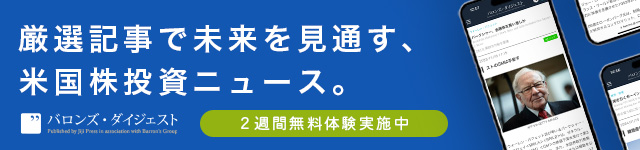サンプル(過去記事より)
2025年の株価はさらに20%上昇する可能性あり
投資家はバブルを受け入れるべきだ
規制緩和とAIが推進役

年末が近づく中、株式市場は急上昇しており、2025年に減速する兆しもない。投資家はバブルの拡大を受け入れるべきだ。
今年の投資は恐らく簡単過ぎた。8月上旬の一時的な急落を除けば、下落局面は極めて少なく、しかも押し目買いの機会として最適だった。米大統領選、海外の紛争激化、インフレ動向と米連邦準備制度理事会(FRB)による利下げ見通しの不透明感など、市場を震撼(しんかん)させるはずだったイベントはあっさりと受け流された。
半導体大手エヌビディア<NVDA>、アップル<AAPL>など、下半期にみられたビッグテックの相対的な軟調も、それ以外の忘れられていた銘柄が注目され上昇する機会にしかならなかった。その結果、S&P500指数は年間で30%近く上昇する見込みで、テクノロジー株中心のナスダック総合指数も年初来で約35%上昇している。
2024年初めにはこうした活況は考えにくかった。当時、株式のバリュエーションは比較的低く、エコノミストはリセッション(景気後退)の兆候を注視しており、投資家のセンチメントは慎重で、FRBはまだ利下げを開始していなかった。
しかし、現在はこのような良い環境では全くない。S&P500指数の2025年予想株価収益率(PER)は約22倍で、バブルに近づいている。経済と市場に対する前向きなセンチメントは、株式からビットコイン、芸術作品に至るまで、アニマルスピリットの高まりに拍車を掛けている。FRBに関する話題の焦点は、もはやいつ利下げをするかではなく、インフレが再燃した場合にいつ利下げを止めるかに移っている。
株式市場が予測可能な存在ならば、市場は急落するはずだ。しかし、株価は2025年もさらに上昇するとみられる。ただし、変動は非常に大きくなる可能性がある。
S&P500指数は、次期トランプ政権の規制緩和と人工知能(AI)の進歩が継続することにより、ウォール街の予想よりはるかに大きく上昇する可能性が大いにある。どちらの要因も単独で市場を押し上げるのに十分だ。二つが合わされば、ロケットが成層圏に上がるように株価は15~25%も急上昇する可能性がある。
しかし、今年に加えて、来年も株価がこれだけ上昇した場合、投資家は難しい決断を迫られる。すなわち、株式の保有を継続して上昇相場に乗るべきか、それとも上昇が続いているうちに利益を確定すべきかということだ。ビーオブエー・セキュリティーズのグローバル株式デリバティブリサーチ責任者、ベンジャミン・ボウラー氏は「バブルが一層拡大する可能性はあるが、その分、崩壊したときの影響も大きくなる」と語る。
ハイテクバブルの再来?

ウォール街は2025年の堅調なパフォーマンスを予想している。ブルームバーグによると、市場ストラテジストによる2025年末のS&P500指数予想の平均は6500付近で、直近の数値を約7%上回る。半数以上のストラテジストが目標値を6500~6700としている。
現在の業績予想に基づくと、S&P500指数のコンセンサス予想は妥当にみえる。ファクトセットによると、ウォール街は2025年のS&P500指数の1株当たり利益(EPS)を15%増の273.25ドルと予想している。2026年のEPSが13%増の309.37ドルで、PERが0.5ポイント低下した場合、S&P500指数は6700強となり、11日の終値を10%上回る。
しかし、過去の市場が合理的であったことはめったにない。ドイツ銀行のデータによると、過去100年間では、株式市場の年間パフォーマンスがプラス0~10%だった年よりもプラス10~20%だった年の方が多い。全体として、株価が20%以上上昇した年の割合は39%で、下落した年は26%だった。アナリストが予想しているような平均的なリターンの年はそれほど多くない。
20%以上の上昇が連続することも少ない。S&P500指数が2年以上連続で20%以上上昇したのは歴史上わずか3回だけだ。最初の事例は1935年と1936年だが、結局1937年に39%急落した。これはFRBの利上げと財政支出削減のタイミングが悪く、世界恐慌を長引かせたためだった。
1954年と1955年の事例はそれよりましで、S&P500指数は1956年に2.6%上昇した。直近の事例は1990年代半ばだ。株価は1995~98年に4年連続で20%以上上昇し、1999年も20%近く上昇した。結局、この上昇相場は2000年のハイテクバブルの崩壊とともに終了し、2002年に市場が底打ちするまでに、S&P500指数の下落率は約50%となった。
ハイテクバブルとその崩壊は繰り返されるのだろうか。その可能性はある。オッペンハイマー・アセット・マネジメントのチーフ投資ストラテジスト、ジョン・ストルツファス氏は12月9日、2025年末のS&P500指数をウォール街で最も高い7100と予想した。その大きな理由はAIテクノロジーの発展だ。ストルツファス氏はAIを1920年代の(大衆向け)自動車の登場になぞらえ、AIが自動車と同様に経済全体の生産性を改善すると予想している。
また、現在の市場にはハイテクバブル当時にはないものがある。それは規制緩和と減税の可能性だ。トランプ次期大統領は、1月下旬から始まる任期中、新たな規制を1件制定したら10件の規制を撤廃すると公約している。この公約を守るのは難しいかもしれないが、特に政府効率化省(DOGE)の設立もあり、規制緩和の推進は次期政権の大きなテーマとなるだろう。
ソシエテ・ジェネラルの米国株戦略責任者、マニシュ・カブラ氏は、金融、製造業、エネルギーがトランプ政権の規制緩和の中心になる公算が大きいと語る。規制が削減されれば、米国の製造業セクターが過去15年にわたって苦しんでいた生産性の低迷から脱する助けになり得る。トランプ氏が第1次政権時と同様に二酸化炭素排出量に関する規制を撤廃すれば、原油関連のエネルギー企業の業績にとって追い風となる可能性がある。金融機関は後払い決済、クレジットカード手数料、大手銀行などのさまざまな規制の緩和によって最大の受益者となるかもしれない。
法人税率の引き下げも助けになるはずだ。税率が21%から15%に低下すれば、EPSは2~3%増加するだろう。カブラ氏は「中小型株は米国内へのエクスポージャーが大きいため有利だろう。当社は中小型株、特に金融と資本財にエクスポージャーを有する銘柄がアウトパフォームすると予想している」と語る。
AIと規制緩和の組み合わせは、利益率と利益を押し上げ、株価を現在のストラテジストの予想よりも大幅に上昇させる可能性がある。カブラ氏は2025年末のS&P500指数を6750と予想しているが、7500に上昇する可能性もあると指摘する。さらに、米国が建国250周年を迎える2026年7月4日には8000に達しているかもしれないと言う。
インフレ再燃の可能性とFRBの手綱さばき

しかし、そう簡単に全てがうまくいくことはないだろう。減税と規制緩和の恩恵は関税と移民の強制送還によって相殺され、差し引きではマイナスとなる可能性がある。カブラ氏は関税によってS&P500指数のEPSが2~3%減少する可能性があると推定する。
インフレが進めば、FRBは利下げを停止し、利上げに転じざるを得ないだろう。さらに、リセッションに陥る恐れもある。失業率が上昇し、他にも景気減速の兆しが現れているにもかかわらず、投資家はリセッションの可能性を忘れてしまったかのようだ。
BCAリサーチのチーフグローバルストラテジスト、ピーター・ベレジン氏は、トランプ減税は第1次政権下で設備投資の増加につながらなかったと指摘し、第2次政権下でも同じだろうと予想している。さらに、貿易戦争の可能性は企業の支出を減らし、消費者にとって強い打撃になるかもしれない。ベレジン氏は「どちらにせよ、われわれはリセッションに向かっている」と語り、2025年末のS&P500指数の目標値をウォール街で最も低い4450としている。
投資家はFRBにも注意する必要がある。FRBは12月に利下げを行い、来年も3回の利下げを行うと予想されている。FRBのパウエル議長は、経済を成長させつつ、インフレ率を低下させるという微妙なバランスを取ることを強いられている。インフレが再燃した場合、利下げとそれに伴う上昇相場はリスクにさらされるだろう。
しかし、FRBが政策を誤り、インフレ率の上昇にもかかわらず利下げを継続し、株価の上昇が促進される可能性もある。調査会社ヤルデニ・リサーチのエドワード・ヤルデニ社長は、「8月のジャクソンホール会議以降、ハト派的な姿勢を維持しているパウエル議長が、12月(18日)の記者会見で非常にタカ派的な姿勢に転じない限り、利下げによって株価は一段と上昇し得る。これは来年初めに株式市場が調整する可能性と、景気が過熱するリスクの可能性を高める」と語る。
バリュエーションも割高に見えるが、見た目ほどリスクは大きくないかもしれない。PERは、コロナ禍からの回復後のピークである2022年とハイテクバブルを除き、史上最も高い水準にある。しかし、調査会社トライバリエート・リサーチの創業者、アダム・パーカー氏は、割高なPERはS&P500指数の構成要素の変化も反映しているという。例えば、以前のS&P500指数は製造業のウエートが大きかったが、現在はテクノロジーとその隣接業界の企業が大半を占めている。収益性も向上しており、利益率が60%超の指数構成企業は36%に上る。
パーカー氏は、AIによって利益が増加すれば、現在のバリュエーションが割安にみえる可能性があると指摘する。さらに、バリュエーションは市場のタイミングを計るツールとしては不便である。バリュエーションの水準は、長期的なリターンを予測するのには役立つが、12カ月後のパフォーマンスとはほとんど相関性がない。
しかし、割高なバリュエーションは不安なものであり、投資家は2025年を通してある程度の居心地の悪さを受け入れる必要があるだろう。ビーオブエーのボウラー氏は、1920年代以来、規制緩和と技術革新が収れんしたことはないと指摘する。両者が同時に起きることで、すでに割高な市場のバリュエーションはさらに上昇する可能性がある。
ボウラー氏によると、ボラティリティーは通常、バブル期に上昇する。そのため、第1次トランプ政権1年目の2017年のように、来年のシカゴ・オプション取引所(CBOE)のボラティリティー指数(VIX指数)が10を下回って推移する可能性は低い。その代わり、ハイテクバブルの後半と同様に、ボラティリティーは株価と共に上昇するだろう。ボウラー氏は「歴史的にみて、バリュエーションがこれほど割高なときはリスクが上昇する傾向があり、市場の方向性にかかわらず株価のボラティリティーは高まるはずだ」と語り、下振れリスクをヘッジするために、現在割安に見えるオプション戦略を利用することを推奨している。
攻めの姿勢が重要

しかし、ディフェンシブな姿勢では、投資家が望む成果を得られる可能性は低い。モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメントのシニアポートフォリオマネジャー、アンドリュー・スリモン氏は、生活必需品やヘルスケアなどのディフェンシブなセクターが年初来でアンダーパフォームしていると指摘する。上場投資信託(ETF)の生活必需品セレクト・セクターSPDR ETF<XLP>とヘルスケア・セレクト・セクターSPDR ETF<XLV>の上昇幅はそれぞれわずか15%と5.7%だ。2025年も投資家がリスクの高いセクターを追いかけ、ディフェンシブ株のアンダーパフォームが続く可能性がある。
スリモン氏は、安定的に成長しており、バリュエーションが割高な銘柄についても、同じ理由で来年、困難に直面する可能性があると懸念している。スリモン氏は「市場は楽観的な段階に入っており、2025年もそれが続くだろう。特にFRBの利下げが見込まれるのでなおさらだ」と語る。
ドイツ銀行のストラテジスト、ビンキー・チャドハ氏は、アニマルスピリッツが戻ってきたことを踏まえ、景気循環の影響を受けやすいセクターへの投資を続けることを推奨している。チャドハ氏は一般消費財、素材、金融をオーバーウエート、生活必需品、ヘルスケア、通信などのディフェンシブセクターをアンダーウエートとする。金融セクターは貸し付けの伸びとM&A(合併・買収)案件の増加から恩恵を受けるだろう。素材セクターは十分に割安であり、経済活動が世界的に加速し、ドル高が後退すれば反発が見込まれる。
2025年に成長と安全の最良の組み合わせを提供するのは大型ハイテク株かもしれない。ウルフ・リサーチのチーフ投資ストラテジスト、クリス・セニエック氏は、マグニフィセント・セブン(M7。グーグルの親会社アルファベット<GOOGL>、アマゾン・ドット・コム<AMZN>、アップル、メタ<META>(旧フェイスブック)、エヌビディア、マイクロソフト<MSFT>、電気自動車メーカーのテスラ<TSLA>)には来年、投資家が求めるものがすべてそろっていると主張する。これらの企業はAIへのシフトから恩恵を受けており、利益成長も依然として力強い。
M7はボラティリティーが再び上昇した場合に役立つディフェンシブな性質も持っている。セニエック氏はエヌビディア、アマゾン、テスラ、メタを選好する。その理由は、景気の影響をより受けやすく、米国の経済成長率が上向くことで恩恵を受けると見込まれるからだ。セニエック氏は「M7は、ファンダメンタルズが今後数四半期にわたって堅調である限り、アウトパフォームを続けるだろう。AIへの熱狂がかなり冷めるなど、『何か』によってミニバブルが弾けるまで、この動向は変わらないとみている」と語る。その「何か」を懸念するのは2026年のことになるだろう。